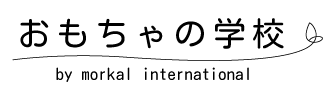「学校に行きたくない」という子どものSOS|行き渋りへの対応に親はどうすればいいのか

突然我が子から「学校に行きたくない!」という言葉を言われると、何があったのか問い詰めてしまいたくなるのが親心です。
しかし、子どもはどうやって伝えたらいいのかわからないことも…。
たくさん子ども自身で考えて、親子で一緒にどうすればいいのか答えを出すことが大切です。
そこで今回は、学校に行きたくない!子どもの生き渋りで親ができる対応についてお話ししていきたいと思います。
行き渋りは子どもたちからのSOS

「学校に行かない」あるいは「学校に行けない」状態にある子どもを不登校状態と言いますが、この項目では小・中学校の90日未満の長期欠席をしている子どもについてお話していきます。
文部科学省の令和4年度資料「児童生徒の問題行動・不登校生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると、不登校に繫がる前段階として、以下の5つの要因があると指摘しています。
| 人数 | 不登校児童生徒に占める割合 | |
| 無気力・不安 | 154,772人 | 51.8% |
| 生活リズムの乱れ、あそび、飛行 | 33,999人 | 11.4% |
| いじめを除く人間関係をめぐる問題 | 22,187人 | 9.2% |
| 親子の関わり方 | 22,187人 | 7.4% |
| 左記に該当なし | 14,814人 | 5.0% |
同資料によると、令和4年度の報告で90日未満の長期欠席をしている小・中学生は小学校で105,112人、中学校で193.936人でした。
90日未満の長期欠席者、そして90日を超える不登校の子どもたちは、ある日突然〝よーいドン〟で学校に来なくなってしまうワケではありません。
上記の表のように学校に行けなくなるまでには、気持ち的な落ち込みや、友人など対人関係での悩みがあったことが調査で明らかになっています。
そして、「今日、学校行きたくないな…」そんなことがぽろっと口から出てしまうこともあったでしょう。
小学生では、親御さんに「学校行きたくない!」と訴えることも珍しくありません。
これはすなわち、行き渋りという〝子どもたちからのSOS〟なのではないでしょうか。
「学校に行きたくない!」行き渋りまでにつながる子どもたちの葛藤
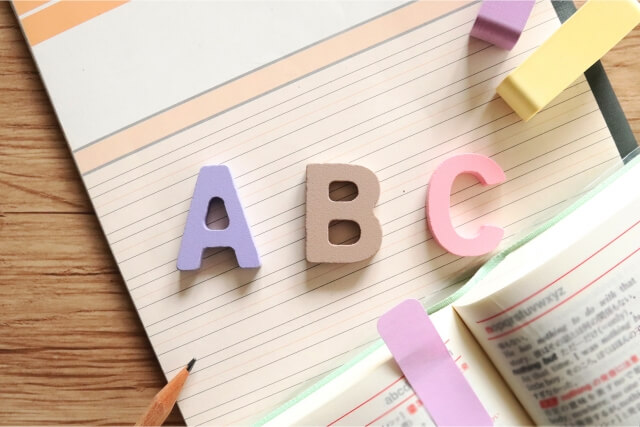
子どもたちが生きる世界は、大人が想像するよりも非常に繊細でむずかしく、また目まぐるしい世界に生きています。
学校では、友だちだけではなく教師との人間関係も築きながら、求められる一定ラインの学業を修める必要があります。そのためには、学校の授業の他に、宿題などの課題の提出もあります。
最近では留守家庭児童会を利用する小学生の子どもたちも増え、そこでは異学年保育となっていくことも多いので、上級生や下級生との関係も築く必要があります。
加えて、家に帰ってきたら習い事行き、習い事の課題をこなし、大人顔負けのハードな日々を子どもたちは過ごしています。
忙しい日常の中で、人と人が関わる世界では必ず〝衝突〟が起こるでしょう。
友だちとケンカしちゃった…、なんか雰囲気悪い…、なんとなくイヤだ…。子どもたちは敏感に空気を読み取り、読み取った空気がストレスになることもあります。
繊細な子どもたちの正解だからこそ、大人が気付かないうちにストレスを抱えています。
しかしそのストレスをどうやって発散すればいいのか、どうやって周囲の大人に伝えたら良いのかわからないことも…。
こうした子どもたちの葛藤が、「学校に行きたくない!」に繫がると私は考えています。
子どもの行き渋りの対応はどうすればいいの?

子どもたちの話を、遮らずにゆっくりと聞くことはとても大切です。
その子どもが理解できる言葉で、十分時間にゆとりをもって子どもの話を聞いてあげてみてください。
1回ではきっと、子どもはどう話せばいいのかわからず「わからない」と答えるかもしれません。
そういうときは、「わかった。じゃぁ、もし話ができるようになったら教えてくれる?」というように、〝次もあなたの話を聞くよ〟と明確に伝えましょう。
まとめ
子どもたちは大人が想像するよりも忙しく、繊細な世界で生きています。
「学校に行きたくない」という子どもの言葉は、大人へのSOSということも。
我が子の「学校に行きたくない!」という言葉に、親は最初驚いていろいろ聞きたくなってしまいますが、ゆっくりと時間をかけて、子どもにわかる言葉を使いながら、子ども自身が親に話してくれるのを辛抱強く待つようにしましょう。