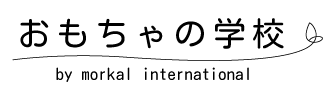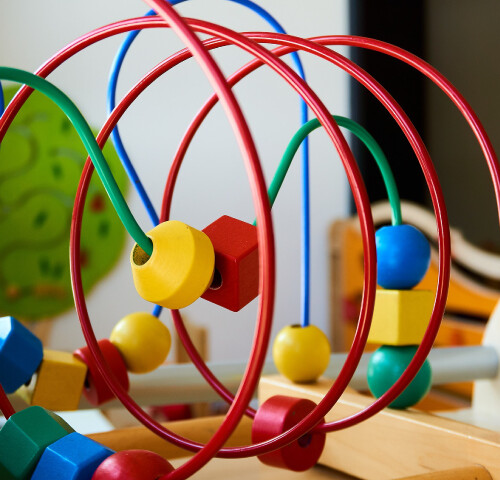1年生の壁とは?4つの原因と対処方法

1年生となってしばらく経過した後は、入学時の緊張がほぐれて親だけではなく先生にも甘えを見せてくれる時期です。
この1年生の時期は、〝壁〟と呼ばれることがあるのをご存じですか?
そこで今回は、1年生の壁を筆者の経験を交えながら紹介していきたいと思います。
1年生の壁とは?乗りこえ方も知っておこう

1年生の壁とは、〝保育園・幼稚園でできていたことができなくなること仕事と子育ての両立の問題〟のことを指します。
小学校と幼稚園・保育園の対応の違いが、「1年生の壁になっている」と言っても過言ではありませんが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
1.子どもを預けられる時間が維持かくなる

留守家庭児童会を利用しない場合は2〜4時間、留守家庭児童会を利用する場合でもこれまでの保育園や、幼稚園の預かり保育のように預かってくれなくなります。
現在小学3年生の長男の場合は、給食着後下校の日もあれば、5時間授業のみ、週に2回だけ6時間という時間割の日があります。
こうしてみると、子どもを児童会に預けないと働くお母さん・お父さんは厳しいかもしれませんね。
私の長男が利用している留守家庭児童会は、別途延長料金が必要ですが、電話で連絡することで電車の遅延や残業などには対応してくれる場合があります。
3.委員会活動が増える

留守家庭児童会を利用する場合、利用者はすべて働いているお母さんやお父さん、介護が必要な家族が居るケース、障害がある児童などさまざまな事情を抱えています。
そのなかで1学期に1回は夜遅くに集まって役員会議が実施されることもあります。
一度役員になれば1年間は何らかの仕事をしなければならないので、大きな負担になることも…。
私が利用している留守家庭児童会は、役員決めも仕事内容もすべてくじ引きで決まったので、文句言い合い子なし状態です。
でも1回経験すれば、今後は免除されるというメリットがあります。
4.子ども自身の心ゆらぎに対応できない

6歳、今年で7歳という小学1年生のお兄ちゃんやお姉ちゃんは、学校に行くことを楽しみにしている子も居ますが、なかではそうではない子も居ます。
学校に行くのは楽しいけれど、児童会がイヤだ。早くみんなと帰りたい。というケースも…。
我が家の長男がこのケースで、毎晩「明日は児童会なの?」「お休みしたい」と私に直談判してきました。
長男は環境の変化に弱く、疲れやすいという特性がある子だったので、〝毎週水曜日は児童会なしの日〟とお互い員決めて、るんるんで帰ってきていました。
子どもにも、大人と同じように「ノー残業デー」のような日が必要なのでしょうね。
この長男のノー児童会デーは、最初のほうは自由に過ごさせていましたが、好きなプログラミングの習い事をはじめて生き生きとするようになりましたよ!
まとめ
仕事と家事、そして育児を両立するにはなかなか現行の支援サービスではむずかしいところがあります。
働き方を工夫したり、仕事の都合が付いたりすれば〝ノー児童会デー〟を作ったり、大人と子どもが気持ちよく留守家庭児童会に通えるように工夫する必要があるのではないでしょうか?
ひょっとしたら早朝村の独自の制度があるかもしれないので、一度児童会の先生に相談してみてもいいですね。