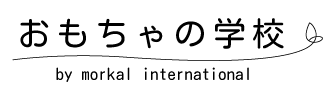どうしてこどもに音楽が必要なの?知育に良い影響を与える理由

幼児向けテレビや、幼稚園、保育園などでは、必ず音楽が流れる時間を設けています。
まだつかまり立ちを覚えたばかりのちいさなこどもが、音楽にあわせて踊ったり、歌ったりする様子は愛らしく、ずっと見ていられるという方も多いでしょう。
しかしなぜ、ここまで小さなこどもと音楽は関連付けられているのでしょうか?
それは、こどもの知育において音楽は決して無視できないほど大きな役割を担っているからでした。
今回は、どうしてこどもに音楽が必要なの?知育に良い影響を与える理由について解説していきます。
なぜ音楽は知育に良いの?

音楽はこどもとのコミュニケーションに欠かすことができないとして、保育園やこども園などの指針になっている厚生労働省の「保育所保育指針解説」にも定められています。
音楽は、自分の体を思うように動かすことができるようになったこどもが、音楽にあわせて思い思いに体を揺らしたり飛び跳ねたり、手や足でリズムをとって遊ぶことができます。
まだ言葉を交わしてコミュニケーションがとれない時期のちいさなこどもも、音楽を聴いて、お父さん・お母さん、きょうだいの真似をして踊ったり、歌ったりして楽しむこともできます。
音楽は、日々の生活のなかで以外と見落とされてしまいやすい知育のひとつです。
人は配列された音を関係づけて聞き、それによって流れる時間は特別なものになります。
さらに、音楽は人の情動や体の動きを促すので、心の発達だけではなく、こどもの運動能力を刺激するにも良い影響を与えると言えるでしょう。
【参照】乳幼児の発達と音楽の関係―音楽の機能が及ぼす影響についての検討を通して―|福岡大学付属図書館 https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/repo/repository/fukuro/R000000552/16-16.pdf
音楽を楽しめる知育玩具3選

音楽を聴いて歌う、踊るという体験は、こどもの知育に欠かせない経験ということを解説してきました。
音楽をより経験させてあげるためには、自分で奏でるという体験も非常に重要です。
なぜなら、自分で奏でることでより注意をして音楽を意識するようになり、自分の考えや思いを表現することができるからです。
ここからは、こどもが自分で奏でることができるおもちゃを3つご紹介いたします。
1.DJECO 楽器3種タンバリン・マラカス・カスタネット

フランスで活躍するデザイナーがデザインした、色鮮やかでユニークなおもちゃが特徴的な「DJECO」の楽器3種タンバリン・マラカス・カスタネットは、リズム感を養うことができる楽器セットです。
3歳から遊ぶことができるおもちゃになっていて、異国を感じる楽しそうな生き物のイラストが描かれています。
2.BONTEMPI トランペット4key37cm

約80年の歴史があるBONTEMPIは、楽器専門のおもちゃメーカーです。
軽くて丈夫なトランペット4key37cmは、ミ・ラ・ド#・ミの音を奏でることができ、3歳から音を意識した音楽遊びができます。
3.ClassicWORLD ファンタジーピアノ

2006年にベルギーでおもちゃの販売を開始したClassicWORLDのおもちゃは、高い品質の木製玩具を、求めやすい価格帯で販売しているのが特徴のおもちゃメーカーです。
ClassicWORLDのファンタジーピアノは、1歳6か月から音を意識してピアノを奏でることができるおもちゃで、こどもの小さな指で奏でられるように、かわいいサイズのピアノになっています。
まとめ
音楽は子供の知育において見落とされやすいですが、小さなこどもが自分を表現するのに欠かせない手段のひとつなので、ぜひ日常生活に音楽を取り入れてみてください。
1歳6か月頃からは、楽器で音を意識して自分で音楽を奏でることもできるようになるので、音楽を聴いて歌う、踊るに加えて、音を意識して自分で表現する力も養ってみましょう。
【おすすめ記事】
楽器に触れてみたい!はじめての子も楽しめる本格的な楽器おもちゃのご紹介 | おもちゃの学校 (toyschool.net)